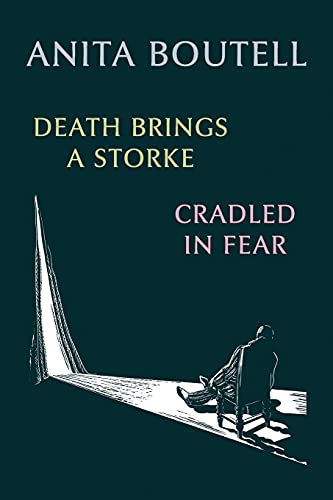読書日記20230702-0703(『幽霊屋敷 新訳版』【★★★☆☆】)
■20230702
ダラダラしながら、本を読んだり、文字起こしの仕事をしたりする。この文字起こしは全部終わったら50万字くらいになる想定。
■20230703
労。日曜日に届くはずだった本が送られてくるが、マンションの宅配ボックスが埋まっていて入れられないとのこと。明日取りに行く。なお、土曜日に届くはずだった本は結局届かずじまい。プリコネのガチャはノー課金ながら天井。フェスでもないのに200連で9枚も星3がすり抜けた。哀しいねえ。
・読んだ本
#以下、そう思って読むとネタバレに見えるかもしれないのでご注意ください#
旧創元推理文庫版は所持しているが初読。
トリックは机上の空論レベル。最後に明かされる「驚愕の真相」(笑)から言って、弾丸が被害者に当たって命を奪う結末になったのは完全に「偶然」の産物だろう。というかそもそもあんな現象は本当に発生するのかいな。化学に絶望的に弱かったカーが物理をきちんと理解しているとは到底思えない。そういえばカーって、別の作品でも拳銃を○○○に○○して不可能犯罪をやっていたなあ……
と、小馬鹿にして終わっていませんか? いやあ、それはまったくカーの意図を読めていない。大間違いです。本作のミステリとしてのキモは「馬鹿っぽい物理トリック」にはありません。本作のポイントは「神秘(カワイイ)は作れる」ということ。カーはこれまで【黒死荘】だの【赤後家の間】だの【妖女の隠れ家】だのと、「何か奇妙で恐ろしいことが起きる『伝承』を持つ場所」を作品上に量産してきた。それに対して、本作の「お屋敷」は、色々な人たちが様々な意図をもって建物に『怪異』を紐づけようとしたことにより「今しも【幽霊屋敷】として定義されんとしている場所」である。言うなれば「これから本物になろうとしている偽物」なのだ。それがジョン・ディクスン・カーの作品の中に置かれ、後押しされることでブーストが掛かる。まるで本物であるかのように見えてくる……おお、偉大なるカーは、自分の作風そのものをネタに使って読者を騙しにかかっているのだ。なんという思い切りのよさだろう。
そう考えると、本作にて導入された超即物的トリックは(別にそれしか思いつかなかったわけではなく)「割と最近作られた【都市伝説的神秘】」を完膚なきまでに解体するために投下された「笑っちゃうほど安いネタ」なのだと気づかされる(上等な料理にはちみつをぶちまけるがごとき思想!! しかしその崩壊こそエクスタシー……)。物語の終盤、フェル博士がやらかす大惨事(とんでもない犯罪だよ)も、40年に出た本書の二年前、38年に出たダフネ・デュ・モーリア『レベッカ』終盤の印象的なシーンを踏まえた「ゴシック屋敷よさようなら」的高踏ギャグなのだと思う(作中の時代が37年なのがまた巧妙)。
以上をまとめると、本作はとにかくギャグ、ジョーク、ナンセンスなのだということ、これに尽きる。そもそもからして「あ、踏んじゃった~テヘペロ」がお笑いでないわけがないのだ。ただ、初見ではそれが分からない。二度読んで初めて、ありとあらゆるものが究極のジョークに奉仕するために組み立てられていたことが分かる。これが重要である。
二度読み必至!とは舌が割けても言うまいが、「ひどいトリックだったな」と投げ捨てて終わりにしては、本書の真価は見えてこない。まあ、そのジョークが面白いか、笑えるかはまた別の話なんですけどね。
読書日記20230630-0701(『すり替えられた誘拐』【★★★★☆】)
twitterがどうもあやふやになりかけているので、ブログで記録を書くことにした。概ね買った本、読んだ本の報告くらいだと思います。
【追記】紹介本タイトル、五段階評価を追加しました。
■20230630-20230701
実家に帰る。理髪店に行く。蕎麦屋で食事。たまには親に外食をおごるのも悪くはないだろう。
・買った本
石川喬司・結城信孝編『黄金の腕』(光文社文庫)
高島俊夫『本が好き、悪口言うのはもっと好き』(ちくま文庫)
・いただいた本
ロバート・アーサー『ガラスの橋』(扶桑社ミステリー)
新刊を編集部から謹呈でいただく。ありがとうございます。
・読んだ本
D・M・ディヴァイン『すり替えられた誘拐』(創元推理文庫)
最近新刊(どころか本自体)をまったく読めていないので、とりあえず安定した作家の作品からリハビリを開始。twitterで読んだと書いている人は皆微妙な口ぶりをしていたのでどのようなものかと思ったが、なるほどこういう作品ですか。
物語の前半では、①大学内で窃盗を行ったという容疑で逮捕された青年の地位回復を求める運動をめぐるいざこざ、②結婚寸前だった女に浮気されて別れたばかりのブライアン(主人公、ギリシャ語講師)の周囲で展開されるストーリー、の大きく二つが並行的に描かれていく。それらを結ぶのが、学内きってのアバズレ(これも死語ですな)女生徒バーバラ。彼女の父親が大学へ莫大な寄付金を出していることから、色々な問題の焦点になっている。彼女を誘拐したと見せかけて大学当局を揺さぶってやろうという学生運動サイドの浅薄な計画が失敗に終わった、と見えて実は……。
ひとつ死体が転がってからは一応探偵小説風な展開を見せる。警察サイドの話は時たま出てくるだけでしかも何の役にも立たないが、それに対して素人探偵たちが独自の立場からあれこれ論理を展開してみせる、といういつものディヴァイン・メソッド……なわけだが、本作ではそれ以前の問題としてヤレヤレ系ムッツリのブライアンに対して、何とか弟の無罪を証明してほしいと媚び媚びで頼み込む、バーバラの愛人マイケル(人間のクズ)の姉のローナがとにかく痛々しい。本当に何考えてんだろ、この女。
謎解きの糸口になるのがイギリスの大学の入試システムであり、内部の人間ゆえの違和感であるというのはちょっと面白い。ディヴァイン自身、大学の事務員であったという前歴がありますからその辺りはお手の物だったのでしょう。
そこで疑惑を持たれた男こそがマイケルを陥れた真犯人だった……という訳で、謎解き自体はここで終了。以降は、真犯人がなぜマイケルを憎悪するに至ったかという人間研究になっていく。本格ミステリを求める読者にとってはがっかりだったかもしれんが、個人的にはここから大フィーバー。「全能感に溢れているが、実態としては有能と言えない勘違い男」と「世の中辛いことばかりだけどきっと誰かが助けてくれる……と信じて努力しない甘え男(自分がすべての元凶なのに何勘違いしているんだ! でもそれを許してしまうダメンズ育ての女たちもクソだよね~)」のダメンズバトルでめちゃめちゃ笑わせていただきました。ブライアンの母親もまた浮気の末に離婚、父親に引き取られたブライアンが母親のことを許せずにいる……というサイドストーリーもあり、この作品が「浮気」(とそれに伴って生じる人々の感情の軋轢)を重要なファクターとして描いているのが分かる。うんうん、イギリス人作家はやっぱりこういうブラックユーモア小説を書いてナンボやねん。個人的には本作を「’60年代の『大転落』」だと評価しています。
「このミステリーがすごい!」や「本格ミステリベスト10」で上位に食い込むことはないだろうが、この作者が好きだという人なら必読の作品だと思う。
<幻のポケミス>から考える「クラシックミステリ叢書」企画
「クラシックミステリの叢書のラインナップを作ってみたい」
「オールタイムベストを作ってみたい」に並んで、マニアであれば一度は思い浮かべるこの夢。かく言う私も過去、本ブログを含めて幾度か作成を試みてきたが、誰も知らない作家の誰も知らない作品を混ぜ込みたい、というかできればそういうものばかりにしてみたいという歪んだ自意識のせいで、反応に困る代物をおったてては、読者の皆様にどう反応すればいいんだよと思わせてきた。
今回、ここに提示するものは、いわゆる<幻のポケミス>をネタ元とするラインナップである。なお、<幻のポケミス>とは、「本棚の中の骸骨」の「読み物と資料のページ」に掲載されたもので、「No.194パット・マガー『被害者を探せ』(1955年7月刊)の巻末に、今後の刊行予定として掲載されたもの(中略)(のうち)ハヤカワ・ミステリでは実現しなかった〈幻の作品〉を抜き出してリストにしてみた」と説明されている。この約160冊のリストのうち、2023年現在をもって未訳の作品が40冊。この40冊を叩き台に、比較的現実的と思える10冊をラインナップしてみた。並びは原著刊行順。作品は基本的に<幻のポケミス>ママとするが、※については作品を変更している。
①ブライアン・フリン『孔雀の眼の秘密』The Mystery of the Peacock’s Eye(1928)
②J・J・コニントン『二枚の切符の謎』The Two Tickets Puzzle(1930)
③デイヴィッド・フロム『スコットランドヤードから来た男』The Man from Scotland Yard(1932)
④ヴァン・ウィック・メイスン『七つの海の殺人』The Seven Seas Murders(1936)※
⑤スチュアート・パーマー『青い小旗の謎』The Puzzle of the Blue Banderilla(1937)
⑥レスリー・チャータリス『輝かしき悪漢たち』The Bright Buccaneers(1938)※
⑦フランシス・ボナミイ『牧場主の死』Death of a Dude Ranch(1939)※
⑧アニタ・ブーテル『死神は過去から来る』Death Has a Past(1939)
⑨レイモンド・ポストゲイト『扉の前に誰かいる』Somebody at the Door(1943)
⑩ローレンス・トリート『警察(ポリス)のP』P as in Police(1970)※
①は英国のスリラー作家の初期作。風変わりな冒険小説のような書き出しで始まるが、スコットランドヤードの警部と私立探偵がそれぞれに出会った事件を捜査するうちに、巨大な陰謀が浮かび上がってくるというプロット。どんでん返しの連発で最後まで飽きさせない。『ミステリリーグ傑作選』所収の長編「角のあるライオン」以外、これまで無視されてきた作家の面目躍如たる傑作である。
②は英国の本格もので「ハンドラム」派の驍将の中期作。『或る豪邸主の死』(長崎出版)、『レイナムパーヴァの災厄』『九つの解決』『キャッスルフォード』(論創海外ミステリ)と、一見渋めながら読者に予想外の衝撃を与え続けてきた作家のシリーズ第七作で、飛び道具多めのラインナップの中ではホッと一息な休憩ポイント。
③はアメリカの女流作家の初期作。複数名義で多くの作品を発表した多作家だが、日本では短編が一本紹介されたきりである。本作はエヴァン・ピンカートンシリーズの第三作で、イギリスを舞台に手堅い警察小説が展開されている。レスリー・フォード名義の作品は現在のコージー派の先駆けとされるが、本作は、80年代以降にアメリカの女流作家が競うように、イギリスを舞台に「理想的な田舎警察小説」を書いたことを思い出させる。
④は日本ではほぼ未紹介(戦前にいくつか翻訳がある)だが、1930年代~40年代のアメリカで絶大な人気を誇った海洋冒険小説作家。その作品のうち、冒険小説と探偵小説をミックスしたのがヒュー・ノース大尉を主人公とするシリーズである。特に初期作は謎解きミステリとしての要素が色濃いとされる。<幻のポケミス>では「作品未定」とされていたため、四つの中編を詰め込んだ本書をセレクトした。
⑤は『ペンギンは知っていた』やクレイグ・ライスとの合作『被告人、ウィザーズ&マローン』で知られる作家の中期作だが、正直この作品にこだわりはない。ガードナー、ライス、スタウト(あるいはラティマー、グルーバー)といった、陽性のアメリカ作家たちが紹介された時に乗り遅れてしまったのがこの作家の不幸だが、今後積極的な紹介者の手で、年に一、二作でも翻訳が進められて欲しいものだ。
⑥は青年義賊「セイント」シリーズの第一短編集で、「クイーンの定員」にも選ばれている傑作集。15作のうち8作が紹介済みではあるが古い媒体のものが多く、続く作品集Boodle(こちらは全作未訳)と併せて新訳刊行する価値は十分にある。本書が好評を博するようであれば、更に「セイント」ものの長編、また中編集がまとめて翻訳されるよう期待する。
⑦はアメリカの女流作家で、犯罪学者のピーター・シェーンが、作者と同名のワトスン役フランシス・ボナミイとともに難事件に挑むシリーズを展開した。<幻のポケミス>では中期以降の、探偵役抜きでワトスン役が事件に関わるというスピンオフ作品が挙げられているが、こういう作品の前にまず作者の普通の筋運びの作品を読みたい、ということで今回は初期作を選定した。
⑧は英国から米国に移住した寡作な女流作家の第三作。同時代には高く評価されていたが次第に忘れられたという作家で、本作などはパット・マガー『七人のおば』や『四人の女』の趣向を先取りしている点などミステリ史的にも見逃しがたいものがある。マーティン・エドワーズLife of the Crimeで高く評価されたこともあり、現在英米でも見直しが進んでいる。
⑨は現在では『十二人の評決』のみで知られる作家の第二作。夕方にユーストン駅で電車から降りた後で奇妙な死を遂げた議員の人生の謎を、同じ列車に乗り合わせた人々をホリー警部が追う中で浮き彫りにしていくという、新聞記者である著者の面目躍如的作品。渋め・重めな内容ではあるが、一読の価値はあると思う。
⑩は『被害者のV』(1945)という作品で警察小説の始祖とされる作者の短編集で、エラリー・クイーン選というところが面白い。16編のうち10編が翻訳あり(ただしほとんどが60年代に翻訳されたきり)ということで検討のハードルは低め。未収録の作品(のうち70年以前のもの)も七作ほどあり、傑作選ということで再編集するのでも良い。
ということで10作をピックアップしてみた。商業でも無理のない、とはいえ文庫では厳しいかという線で作ってみたがどうだろうか。これを参考にどこかの出版社が本を出し始めたりしたら面白いですね。利用料は取りませんので、どうぞご自由にご使用ください。
【過去の実績】
2022年に購入した洋書について(古書編)
新刊書に続いて古書編も。こちらは個々の本についてもう少し詳しく書いておく。
購入冊数:11冊
・John Dollond A Gentleman Hangs
色々な意味で、今年最大の当たり。M・Kさんが『ある中毒患者の告白』で読みやすさ・総合点ともに高く評価しているにもかかわらず、作品・作者とも情報が一切ネットに出てこない謎の本(バーザン&テイラーが高評価しているらしいと後で知った)。森英俊さんの書庫で見かけて「持っている人は持っているものだなあ」と感心していたが、長年の探索が実りついに発見しました。いかにも知られざる珍本らしく、送料込み10ドルで入手できたのが面白いでしょう。英米のマニアたちを出し抜き、やったやった!と欣喜雀躍してfacebookで自慢しても全く反応がなかったのがいい思い出w
・Jonathan Stagge The Scarlet Circle【ペーパーバック版】
今年の神保町の洋書まつりでは正直得るものがなかったのだが、その二週間ほど前に羊頭のペーパーバック棚でこれを抜いたために歯車がずれたのではないかと思っている。電子書籍でも買ったが、再三ツイッターで書いたようにこの電子書籍版は極めて質が悪い(誤字脱字が多数)ので、紙版を確保する意義は大きい。
・Henry Wade Lonely Magdalen【ペーパーバック版】
・Curtis Evans The Spectrum of English Murder
ヘンリー・ウェイド作品はそのほとんどが電子書籍化されていて入手容易な状況だが、マーティン・エドワーズが絶賛するこの中期作だけはなぜか電子書籍版が存在しない。元版の、特に「改訂前」の戦前版は超入手困難(オークションで三桁後半ポンドで落札されたのを見たことがある)だが、10年ほど前に出たペーパーバック版は、奥付的には戦前版のテキストを使用しているとのこと。真偽を確かめるべくエヴァンズのウェイドについての評論書を購入したのだが……後に小林晋さんが本人に確認したところ、戦前版は未読・改訂内容はノーチェック、という事実が明らかになった。
・W. F. Harvey The Beast with Five Fingers
British Library Crime Classicsの新刊で出たThe Mysterious Mr. Badmanの解説でエドワーズが、「ハーヴェイの没後に出た短編集The Arm of Mrs. Eganはミステリ作品集として秀逸」と書いていたのを見て読みたくなって購入。この、10数年前にでた新しい傑作選は今出ているハーヴェイの本の中ではおそらく最も充実した内容で、上の短編集の収録作もすべて採録。面白い作品があればRe-ClaMなどで紹介したいと考えている。
・Anita Boutell Death Has a Past
・Anita Boutell Death Has a Storke/Cradle in Fear
・J. de N. Kennedy Crime in Reverse
・Leonard O. Mosley So I Killed Her
マーティン・エドワーズThe Life of Crimeに登場、その紹介があまりにも面白そうだったので買ってしまった本たち。このうちでは特にアニータ・バウテルが興味深々な作家で、Death Has a Pastはパット・マガーに先行する「誰が誰を殺したか分からない」ままプロットが進んでいく話らしい。ケネディやモズリーといった作家は、バークリーの後から出てきてシニカルな作品をいくつか書いた「性格悪の悪童たち」とのこと。
・Donald Henderson Mr. Bowling Buys a Newspaper
・Ellen Nehr Doubleday Crime Club Compendium 1928-1991
自分への誕生日プレゼントのつもりで買った本。ヘンダーソンは翻訳希望の作品で、電子書籍も再発された紙版の本も確保済みだが、あくまで原テキストを求めて購入。エレン・ネールはアメリカの「ダブルデイ・クライム・クラブ」の情報を集約した極太本。去年買ったThe Hooded Gunman(「コリンズ・クライム・クラブ」の極太本)と対になる本で、買えてよかった。値段的には今年買った本で一番高い本(送料込み120ドルくらい)。超円安になる前に買ってしまってよかった~。
2022年に購入した洋書について(新刊書編)
まとめを書いておかないとうっかり年を越すので早め早めに。
購入冊数:31冊(うち、実本は12冊)
・kindleで買ったもの(著者名順)
Margot Bennett The Widow of Bath (kindle)
Dorothy Bowers Fear for Miss Betony (kindle)
Dorothy Bowers The Bells of Old Bailey (kindle)
Joan Cockin Villany at Vespers (kindle)
Martin Edwards The Edinburgh Mystery (kindle)
Martin Edwards The Life of Crime (kindle)
Bernard J. Farmer Death of a Bookseller (kindle)
W. F. Harvey The Mysterious Mr. Badman (kindle)
ed by Tony Medawar Bodies from the Library 5 (kindle)
ed by Tony Medawar Ghosts from the Library (kindle)
James Quince The Tin Tree (kindle)
James Quince Casual Slaughter (kindle)
John Rhode The Venner Crime (kindle)
Harriet Rutland Knock, Murderer, Knock! (kindle)
Harriet Rutland Bleeding Hook (kindle)
Harriet Rutland Blue Murder (kindle)
Jonathan Stagge Murder by Prescription (kindle)
Jonathan Stagge Turn of the Table (kindle)
Jonathan Stagge The Scarlet Circle (kindle)
英米の電子書籍は値段が抑えめで積むのに心理的な障害が少なく、良くないと思います(他責志向)。ボワーズは論創の解説の資料として買ったが拾い読み止まり。小説系で全部読んだのはジョン・ロードのThe Venner Crime(Re-ClaM8にレビューあり)と、ジョナサン・スタッジのMurder by Prescription・The Scarlet Circle(Re-ClaM10にレビュー掲載予定)くらい。メダウォー本も面白そうなところだけ拾っただけ。来年はもう少し読みたいところ。
完全新刊では、マーティン・エドワーズThe Life of Crime(Re-ClaM9にレビューあり)を読み切ったのは我ながら偉い! クラシックミステリ好きには堪らぬ小噺が満載の関連書で、「ミステリ史」としては弱い部分もあるが邦訳希望。ただ分量がとんでもないことになっているので、まずは出してくれる版元を探すところからですね。
・実本で買ったもの(著者名順)
Christianna Brand Green for Danger
Christianna Brand Death of Jezebel
Martin Edwards This Deadly Isle
Martin Edwards The Life of Crime
Bryan Flynn The Case of Elymas the Sorcerer
Bryan Flynn Conspiracy at Angel
Bryan Flynn The Sharp Quillet
Bryan Flynn Exit Sir John
Bryan Flynn The Swinging Death
Colin Larkin Cover Me
E. C. R. Lorac Post After Post-Mortem
Patrick Quentin Death Freight and Other Murderous Excursions
ブランドはせっかくなので紙で買いたかったんですよ(声を大にして)。来年は『自宅にて急逝』の元本も予定されているので購入予定。本邦でも評価が高い割りに50年代末から60年代初頭の「初期ポケミス」の訳が生き続けてしまっているのがブランドの残念なところ(これは文庫化時に新訳しなかった早川の罪、『疑惑の霧』の残念さを見ろよ見ろよ)。創元はクリスティーを出し続けるならブランドを早川から奪ってくれんかね(クリスティーの方が安定して売れるのは分かるけど)。
小説の中ではロラックのPost After Post-Mortemを読んでいる。森英俊さんの思い出の一冊(インタビューはRe-ClaM7に掲載)で、原著は間違いなく超レア。ただ、お話としては超ゆったりペースで読み切るのは結構辛かったです。つまらなくはないけど。毎年恒例のブライアン・フリン祭りは中期から後期序盤へ。正直もうどれが面白いのか分からない。来年こそは初期10作から何作かは読みたいところです。パトリック・クェンティンの中編集は、米丸さんがやる気満々なのでそちらに期待。あとは、編者のエヴァンズがクェンティンの評伝を出してくれたら最高なんだけど、来年あたりどうですか。
ちなみにエドワーズ本は、The Life of Crimeは紙で買い直し。This Deadly Isleは本というよりは「地図一枚」。日本だと雑誌の付録で付いてきそうな代物で、1800円だかはボリ過ぎじゃないかしらん。エドワーズマニアなので買うけどね。
→古書編に続きます。
【古典探偵小説架空叢書】クラシックカルトコレクション 第Ⅱ期について
「エディション・プヒプヒ」の垂野創一郎さんがこのような面白い記事を書いていたので、乗っからせていただこう。
以前、私はアントニイ・バークリー書評集第6巻の会場限定おまけとして「クラシックカルトコレクション第Ⅰ期 内容見本」というものを作ったことがあった(2017/5)。そこに載っていたのが以下の五作品。
1. George Bellairs, The Dead Shall Be Raised, 1942 『やがて死者は語りだす』
2. J. Jefferson Farjeon, Mystery in White, 1937 『白雪の殺人』
3. Roger East, 25 Sanitary Inspectors, 1935 『二十五人の衛生検査官たち』
4. Alexander Williams, The Hex Murder, 1935 『黒魔術殺人事件』
5. Ianthe Jerrold, The Studio Crime, 1929 『スタジオの犯罪』
今見ると、当時の復刊作品を並べたのが丸分かりでいささか安直だ。とはいえH・R・F・キーティング推薦のロジャー・イーストや、ブリティッシュ・ライブラリー叢書が軌道に乗るのを助けたジェファソン・ファージョンのスリラー小説などは今でもやってみたいと思っている。アレクサンダー・ウィリアムズのオカルトミステリも面白そうなんだけどな(未だに読んでいない)。
今回はその第Ⅱ期内容見本ということで、出してみたいなあ、自分自身翻訳で読んでみたいなあという本を12冊並べてみた。森英俊氏やM.K.氏、また海外マニア兄貴たちの影響を受けていることがバレバレのちと気恥ずかしいリストである。基本的に「持っている本」から作っているので、Twitterなどで名前を挙げたことがある本も多いかも。ご照覧あれい!
1. Donald Henderson, Mr. Bowling Buys a Newspaper, 1943 『ボウリング氏、新聞を買う』
2. Elizabeth Curtiss, Nine Doctors and a Madman, 1937 『研究病棟の殺人者』
3. Jonathan Stagge, The Scarlet Circle, 1943 『死の紅輪』
4. Theodore Roscoe, I'll Grind Theire Bones, 1936 『巨人の碾き臼』
5. Anita Boutell, Death Has a Past, 1939 『殺意の因果』
6. John Dollond, A Gentleman Hangs, 1940 『首吊り紳士』
7. Marcus Magill, I Like a Good Murder, 1930 『世にも楽しい殺人』
8. Virginia Perdue, Alarum and Excursion, 1940 『軍靴の音が聞こえたら』
9. Libbie Block, Bedeviled, 1947 『悪夢に憑かれて』
10. Richard Hull, Murder Isn't Easy, 1936 『殺人は容易じゃない』
11. James Quince, Casual Slaughters, 1935 『思いがけない大虐殺』
12. 『クリスチアナ・ブランド単行本未収録短編傑作選』(オリジナル編集)
番外:Virginia Cowles, Looking for Trouble, 1941 『トラブルを求めて~特派員欧州を駆ける』
以下、簡単に補足をば。
1. はチャンドラーの「簡単な殺人法」で絶賛された作品。女を殺してしまった男が、警察の捜査状況を確認しようと毎日似合わぬ安新聞を買うが、死体は一向発見されない。折しもロンドンは大空襲の真っただ中で、警察も余裕がないのだ。安全圏にいるはずの男の心は、しかし少しずつ追い詰められていく……ヘンダーソンは、類まれなセンスを持ちながらそれを開花させる前に亡くなった夭折の犯罪小説作家。
2. はクェンティン『迷走パズル』と同時期に刊行された「病院ミステリ」。あちらが精神病院なら、こちらは研究病棟である。精神薄弱者を思うように操るという悍ましい研究に従事していた医師が特殊なナイフで殺されるが、捜査が進むうちに殺人者は病棟に務める医師たちの中にいることが判明して……ある海外マニア兄貴のブログの記事には「謎解きミステリの暗黙のルールを破った」とあるが、果たして?
3. はパトリック・クェンティンの別名義、ジョナサン・スタッジの代表作の一つ。被害者の首に口紅でぐるりと赤い輪を描く連続殺人鬼の凶行に挑むウェストレイク医師の活躍が描かれる。シリーズの中では比較的早い時期に連載されたが、当時コピーキャット殺人(と疑われる事件)が起こったためにお蔵入りとなり、数年後にようやく単行本化されたという経緯がある。スタッジはもっと翻訳されていいと思う。
4. は『死の相続』でご存じセオドア・ロスコーの長編。新聞記者の主人公たちが見守る前で、仏独(を思わせる架空の国)の両首脳が二人きりで会談していた室内で同時に射殺されるという密室殺人事件が発生。この事件をきっかけに欧州情勢は急激に悪化していき、遂には二度目の世界大戦の幕が開く寸前に……不可能犯罪ものであると同時に「近未来シミュレーション小説」としても面白いパルプ小説の傑作。
5. は最近Twitterでも取り上げた「誰が誰を殺した?」ミステリの先駆的作品で、マーティン・エドワーズが評論書 The Life of Crime で取り上げているのを読んだことから興味を持ちました。憎み合う女六人がイングランドの片田舎の屋敷に集まって始まるのはもちろん殺人事件。作者は友人から聞いた話と、彼女から提供された「告白書」の内容を基に殺人ミステリを仕立て上げていく。
6. はM.K.『ある中毒患者の告白~ミステリ中毒編』で大絶賛されたことで記憶に残る作品。ネタ元を手繰っていくとバーザン&テイラーらも褒めているらしい。殺人事件の法廷を見学して帰ってきた主人公たちは、自宅で見知らぬ男の首吊り死体を発見し……というショッキングな幕開けから、軽やかなテンポで物語が展開されていく。一冊きりで消えた作家の超レア本だが、先日10ドル程度でゲットした。ヤッタネ。
7. はこれまた『ある中毒患者の告白』案件。恥ずかしげもなくつぎ込んでいくねえ。主人公と若い友人たちがレストランで殺人ミステリ談義をしていたところ、近くの席で実際に殺人事件が起こってしまうという話。主人公たちはもちろん素人探偵団を結成し、警察に負けじと事件の捜査を始めるが……ユーモラスな掛け合いが楽しい作品だが、中盤以降予想外の方向へと突っ走り始めるのが楽しい。
8. はまたまた『ある中毒患者の告白』案件。石油製品の研究所で起こった爆発事故の結果、記憶を失い病院に入院させられた主人公。果たして彼が失った記憶とは一体何だったのか? 記憶喪失者が、時折フラッシュバックする謎めいた記憶の断片を基に己の記憶を復元していく話が政府筋の陰謀と絡み、読み始めた時にはまったく想像していなかったところに連れていかれる。ニューロサスペンスの秀作。
9. はうだつの上がらない夫を殺して愛人と新たな生活を始めようかと考えていた女が、何者かに先に夫を殺されてしまう……という話が、「信頼できない語り手」の「信頼できない記憶」によって引っ掻き回されていく。果たして私は探偵役? それとも殺人者? 8. もそうだが、50年代にミラーやアームストロングがジャンルを完成させる以前に連発された評価の定まらない作品をもっと読みたい。
10. はご存じリチャード・ハルの第四作。殺人を目論む三人の男たち。ところがなんと、ターゲットは全員同じだった。彼らは互いに互いの殺意を知らないまま、じくじくと憎悪を滾らせ机上の計画を転がし続けるが、全員にとって思いもよらない事態が起こり……ハルの初期作はもっと紹介されるべきだと思うなあと考えつつ、でも日本のミステリシーンでは受けないのかなあと悶々しております。
11. はエドワーズやエヴァンズ大兄など尊敬するレビュアーが褒めているので注目していたら、なぜか電子専売の1ドル本として出てしまった。イギリスの片田舎で起こった連続殺人事件の謎を聖職者作家が描いたという楽しげな作品で、地味ながらユーモアたっぷりなのが嬉しい。
12. は「何をやってもいい」ならこれをやるしかない!という企画。本ブログの読者であれば、ブランドの未発表短編が近年次々に紹介されていることをご存じでしょう。読んでみると、意外やいずれも水準を超えている(どころか傑作もある)。さらに、発表済みでも単行本に入っていない作品も多数。出版社各位、これらをまとめないのは愛読者たちに不誠実ですぞ。仮目次はこんなところでいかが?
・邦訳単行本に未収録の作品
「拝啓、編集長様」/「ダブル・クロス」/「幽霊伯爵」/「大空の王者」/「至上の幸福」/「未亡人に乾杯」
・単行本に未収録の作品・未発表の作品
"Bank Holiday Murder" / "Cyanide in the Sun" / "The Rum Punch" / "The Face" / "The Shadowed Sunlight"
最後に番外として、非小説作品を。ヴァージニア・カウルズは、特派員として1930年代末から40年代前半に熾火燻るヨーロッパを、スペイン動乱、ナチスドイツによるポーランド侵攻、急速に左傾化するフランス、空襲下のロンドンと駆け巡り、「トラブルの最前線」を張り続けたアメリカ人の新聞記者。本書は彼女が帰国直後に刊行した回想録で、その迫力は現在読んでもまったく古びることがない。
この辺の本については、今後別冊Re-ClaMに入ってくるかもしれません。その折はご愛顧のほど、何とぞよろしく。あ、企画重複は大歓迎ですが、そのときはぜひ解説書かせてください、オナシャス!
「奇想天外の本棚」(国書刊行会)刊行予定情報まとめ(2022/9/18時点)
これまでもtwitterやfacebookにて度々「刊行予告」を出してきた編者氏が、先日「第一回配本間近なので、二期以降順不同で発表します。」ということで、大量の刊行予定情報をtwitterにて投稿された。
以下、現状国書刊行会HPにて「第一期」として発表されているものを除いた分の情報を整理する。なお、明らかな誤り(作者名の綴り間違いなど)は修正している。またナンバーについては、氏のツイートのものには重複や脱落が多く見られたため、単純に登場順に振り直していることをお断りしておく。
※タイトルの後ろに付した■は新訳(50-60年代に旧訳あり)を、★は「10年留保の対象外」を示す。
---
13:Philip MacDonald, The Polferry Mystery, 1931 『ポルフェリーの難問』
14:Francis Bonnamy, The King Is Dead on Queen Street, 1945 『王、女王街に死す』
→「幻のポケミス」の一冊(http://www.green.dti.ne.jp/ed-fuji/column-pocket.html)
15:Harry Stephen Keeler, Sing Sing Night, 1928 『歌う歌う夜』
16:Harry Stephen Keeler, The Amazing Web, 1930 『驚愕の蜘蛛の巣』
17:Miles Burton, Three Corpse Trick, 1944 『三つの死体のトリック』
18:Philip MacDonald, The Link, 1930 『輪』
19:John Dickson Carr, The Island of Coffins, 2021 『棺桶島』→カーのラジオドラマシリーズ『B-13号船室』のシナリオ全訳、Crippen & Landru刊。
20:John Dickson Carr, Poison in Jest, 1932 『毒の戯れ』■
21:John Dickson Carr, The New Canterbury Tales, 未刊行 『新カンタベリー物語』→カーが学生時代に書いた連作短篇、単著収録は2022年にCrippen & Landru刊予定の The Kindling Spark が初。
22:Philip Jose Farmer, The Adventure of the Peerless Peer, 1975 『シャーロック・ホームズ/ザッハクラウトの冒険』★→以前も「H・P・ファーマー」と表記して間違いを指摘されている、『ドタバタSF大全集-別冊奇想天外3-』からの再録+αを想定?
23:J. F. Suter, Old Land, Dark Land, Strange Land, 1996 『古い土地、暗い土地、奇妙な土地』★→上記短篇集ではなく、1970年以前の短編のみのオリジナル編集版か?
24:Robert Bloch, Nightmares, 1961 『悪夢』→ロバート・ブロックの短篇書誌はかなり複雑だが以下整理してみよう。
①Nightmares は、Arkham Houseから出た二冊の短篇集を再編集した短篇集の上巻にあたる(下巻は翌年に出た More Nightmares)。
②収録作から見て Nightmares は Pleasant Dreams -- Nightmares (1960) の抜粋版と言える。
③その Pleasant Dreams -- Nightmares は『楽しい悪夢』としてハヤカワ文庫NVから刊行されている。
④Pleasant Dreams -- Nightmares 収録作のうち一部の作品(「影にあたえし唇は」「灯台」「地獄行き列車」)は『楽しい悪夢』に収録されていないが、後のオリジナル編集の短篇集に別途収録されている。(『ポオ収集家』『ハリウッドの恐怖』)
結論:中途半端な Nightmares を新訳刊行するくらいならその元版である Pleasant Dreams -- Nightmares を翻訳する(=並び順をArkham House版準拠とし、更に Nightmares に収録された序文も併せて収録する)方が意義がありそうに思える。(追記)
25:James Gould Cozzens, Castaway, 1934 『デパート漂流』
26:Hilda Lawrence, Death of a Doll, 1947 『人形の死』→『墜ちた人形』として2000年に小学館文庫から刊行されている。
27:Mabel Seeley, Listening House, 1938 『耳すます家』■
28:Christopher Fowler, The Victoria Vanishes, 2008 『ヴィクトリア消失』★→内容は不明だが、本邦未紹介シリーズの第六作をいきなり出すのは冒険的。
29:Hilary St. George Sanders, The Sleeping Bucchus, 1951 『眠れる酒神』→ピエール・ボアローの初期長編『三つの消失』(『大密室』(晶文社)収録)を著者の許可の上で翻案したものらしい。
30:Jackson Gillis, The Killers of Starfish, 1977 『ヒトデの殺人者たち』★→テレビドラマ『刑事コロンボ』などで脚本を提供している作家。
31:Leo Bruce, Case with 4 Clowns, 1939 『四人の道化師の事件』
32:Daniel F. Galouye, Dark Universe, 1961 『暗闇世界』
33:H. H. Holmes, Rocket to the Morgue, 1942 『死体置き場行きロケット』■
34:Anthony Boucher, The Case of the Seven Sneezes, 1942 『七つのくしゃみ事件』
35:Anthony Boucher, The Case of the Seven of Calvary, 1937 『ゴルゴタの七』■
36:Joyce Porter, Dover: The Collected Short Stories, 1996 『ドーヴァー警部捜査せず』★→上記短篇集ではなく、1970年以前の短篇のみのオリジナル編集版か?
37:Stephen Barr 『スティーヴン・バー短篇集』→原書未刊行、雑誌掲載作を集めたオリジナル編集版を想定?
38:Hilda Lawrence, Blood upon the Snow, 1944 『雪の上の血』■
39:William Mole, Skin Trap, 1957 『皮膚の罠』
40:Thomas Sterling, The Silent Siren, 1958 『歌わない人魚』
41:Ed Lacy, Dead End, 1959 『行止まり』■→Dead End は『さらばその歩むところに心せよ』(Be Careful How You Live)の別題との由。確かに新刊で手に取れるに越したことはない作品だが……(追記)
42:Harry Kurnitz, Invasion of Privacy, 1955 『殺人シナリオ』■
43:Rob Reef, Tod eines Geistes, 2019 『幽霊の死』→FacebookのGADコミュニティでよく見かける投稿者で、1930年代のイギリスを舞台にクラシックな作風のミステリを書いている作家のシリーズ第五作。自分の本を読んで評価してくれる人がいないと嘆いているのがよく観測されるので、翻訳されたら喜びそう。(追記)
44:Christopher Bush, The Case of the April Fools, 1933 『四月の魚事件』→仮題と完全に該当する作品がないが、"April" 繋がりでこの作品ではないかと推測されている。(追記)
45:Thea von Harbou, Metropolis, 1927 『メトロポリス』→フリッツ・ラングの映画のシナリオ?
46:Louis Zangwill, A Nineteenth Century Miracle, 1897 『19世紀奇跡の怪事件』
47:Eric Frank Russell, And Then There Were None, 1951他 『そして誰もいなくなった』→表題作を含む中篇集。
48:Arthur Morrison, The Dorrington Deed-Box, 1897 『悪党探偵ドリントンの証文函』
49:S. A. Duse, Doktor Smirnos Dagbok, 1917 『スミルノ博士の日記』■
50:Peter Dickinson, The Yellow Room Conspiracy, 1994 『黄色い部屋の陰謀』★
51:Helen Eustis, The Holizontal Man, 1946 『水平線の男』■
52:Christopher Bush, Cut Throat, 1932 『喉切事件』■
53:James Hadley Chase, No Orchids for Miss Blandish, 1939 『ミス・ブランデッシュにやる蘭はない』→無削除初版を底本とするとのこと。
54:Algis Budrys, Rogue Moon, 1960 『無頼の月』→アトリエサードが随分前から刊行予定を挙げている。
55:Curt Siodmak, Gabriel's Body, 1991 『ガブリエルの身体』★
56:Christianna Brand, Cat and Mouse, 1950 『猫とねずみ』■
57:Christianna Brand, The Chinese Puzzle, 未刊行 『中国パズル』→名のみ聞くコックリルものの未刊行長編。
58:Michael Venning, Murder Through the Looking Glass, 1943 『鏡の国の殺人』→『もうひとりのぼくの殺人』として2000年に原書房から刊行されている。
59:Agatha Christie, The Hollow, 1951 『ホロー館の殺人(戯曲版)』→『ホロー荘の殺人』の戯曲版。日本公演の際には瀬戸川猛資が翻訳したと聞くがそれを採録するのか?
60:S. A. Steeman, Un dans trois, 1932 『三人の中の一人』■
---
私は個々の作品について出来不出来の観点から収録の是非を語る立場にないが、26や58のようなここ20年ほどで翻訳刊行された作品、また、57のようなテキスト自体が未刊行の「幻以前の作品」が含まれていることに企画自体の危うさを感じてしまう。チェック機能が働いていないのではないだろうか?
また、翻訳権取得の問題もある。1970年以降刊の作品は翻訳権取得が必須だが、編集部がそれを無条件に認めるかは分からない(第一期作品でも、エドワード・D・ホックの作品は要取得)。また「短篇集が出たのは近年でも、オリジナルテキストを初出誌から採っているから翻訳権取得の必要はない」というのは常套的な言い抜けだが、カーのラジオドラマシナリオや初期作品において、Crippen & Landru の書籍を底本とするのであれば(道義的には)翻訳権フリーにはならないだろう。
同じく翻訳権取得の問題でも、「海外の著作物の翻訳が10年出ていないときには、日本ではその作家の翻訳+印刷による複製の権利が切れる」の条文がネックになる場合もある。例えば56は「原著刊行1950年、翻訳刊行1957年」である。ブランドは88年に亡くなったので、再度の翻訳刊行に当たって翻訳権取得が必須なのではないだろうか(ただし、翻訳権の問題については個々の作品で状況が異なるため一概には言えない)。
上記のリストを公開する上で、編者氏がこういった事情も全て加味しているのか、あるいは思いつくままに並べただけなのかは分からない。本当にこれらの作品が新訳で書店に並ぶ未来が訪れるのであれば興味深いが、そもそも第一期12冊が出揃っていない(というか一冊も出ていない)現状を鑑みれば、あまり先々のことを考えると鬼が笑い死にするというものだろう。「幻のポケミス」じゃあるまいし。
(追記)2022/9/19 ご本人のツイートにて、クリストファー・ブッシュが重複していたので再検討し、以下の6冊を追加するとの由が発表された。
61:Anthony Boucher, The Case of the Solid Key, 1941 『硬い鍵の事件』
62:Philip MacDonald, Persons Unknown, 1931 『正体不明の人物/推理の演習』→『迷路』として2000年にハヤカワ・ミステリから刊行されている。ただし、挙げているのは先行する米版のタイトルで、英版を底本としているだろう早川版と内容が異なる可能性がある。
63:Ed. by Tony Medawar, Bodies from the Library, 2018 『図書館からの死体』→過去にレビューを書いたことがあるので貼り付けておく。未紹介の良作ももちろんあるが、既訳率が結構高いのが気になる。
64:Noël Vindry, La Bête hurlante, 1933 『吠える獣』→中川潤氏訳による『獣の遠吠えの謎』が本年刊行された。書影は近年翻訳された英版のものだが、中川氏が翻訳を担当するのではないのか?
65:Nicholas Blake, There's Trouble Brewing, 1937 『悪意の醸造』■
66:John Dickson Carr & Val Gielgud, 13 to the Gallows, 2008 『13の絞首台』→カーの演劇台本。ギールグッドと共作した二篇+カー単独の二篇を収録。
(追記2)2022/9/20 初投稿時に「詳細不明」としていた41,43,44について、編者氏のFacebookの投稿を参考に、現状分かる限りの情報を追加した。
【ネタバレあり】ジョン・ロード『デイヴィッドスン事件』(1929)
どう感想を書こうとしてもネタバレになってしまうので、ブログに書くことにする。というか以下のあらすじすらネタバレを回避するために、やや捻った書き方になっている。「クリックで展開」以降は決定的ネタバレなので、クリックは注意。
あらすじ:
デイヴィッドスン社の社長ヘクター卿は酒癖や女癖が悪く、会社の経営にもほとんど興味がない。彼は先代社長であった父の死後に働き者のいとこガイを追い払い、今また様々な発明で会社に大きな利益をもたらし続けてきたエンジニアのローリーを放逐して資産を独り占めしようとしていた。ところが土曜日の夜、サマセット州のとある駅からデイヴィッドスン家の別邸へ向かう荷馬車で心臓を刺されたヘクター卿の死体が発見される。そして、馬車が運んでいた大荷物入りの籐のケースはどこかに消えてしまった。ケースも殺人犯も見つけられない地元警察へと派遣されたロンドン警視庁のハンスリット警部は、プリーストリー博士に協力を要請する。
感想:
ジョン・ロードは(少なくとも既に翻訳されている作品では)「丁寧な証拠の収集」「証拠に基づく仮説の構築」「仮説についての論証の展開」によって物語を構成する作家である。その軸には「意外な結末」への強い志向があり、そのためには奇想天外なトリックを弄することすら辞さない力強さがある。
しかし本作はその「三段階の構成」が緩い。というのは、プリーストリー博士が事件にあまり介入しないからだ。友人であるガイからヘクター卿の検死審問への同行を依頼されても助手のハロルドを派遣して済ませているし、事件の関係者に直接話を聞くこともほとんどしない。犯人に目星を付けた後に、アリバイトリックを解き明かすヒントをその自宅でつかみ警察に提供したりしているが、全体的に活動は消極的だ。このシリーズにおいて、博士は謎とその解決を楽しむが、本業に差し支えるほどの深入りはしないという設定になっている。とはいえその彼が事件に対してまるで「他人事」のような対応をしているのが、本作の特徴である。
▼クリックで展開
この「特徴」がまさか、本作の趣向のための仕込みとは仏様でも思うまい。
さて物語の続きは……結局証拠は一向に挙がらず、警察は間接証拠だらけの訴因で裁判に持ち込んだ挙句、揚げ足を取られて敗訴。ほとんど行動を起こさなかった博士はただ警察に失望されて、事件はバタバタと幕を下ろす。いわば「名探偵の敗北」だ。「一事不再理」のルールがある以上、法的にはもはやガイを捕らえることはできないと警察は諦めてしまうが、ただ真実にのみ興味を持つ博士は、そこから証言の見直しと証拠の洗い直しを行って真のトリックを見破り仮説を再構築、真相を突き止めてガイと再び対峙する。
正直、事件を構成する上で犯人が使った「人物入れ替わり」と「ケースの中身の入れ替わり」を組み合わせた二重の入れ替えトリックは、分かりやすい各種伏線からあっさり見抜くことができた(むしろダミートリックの方が後出しで想像不可能)。そのため作品の読み味は個人的には倒叙に近く、プリーストリー博士はどのタイミングで真犯人ガイの計画の決定的な瑕疵を見抜いて、その物的証拠を叩きつけるのだろうと楽しみにしながら読み進めたが、その想像は裏切られた。「本命トリックとは別にレッドへリングのダミートリックを走らせることで捜査側の目を欺く。そのためには一度は逮捕され、裁判に掛けられるのさえ耐えてみせる」というあまりに大掛かりな操りの構図はなるほど斬新なアイディアだし、多くの読者を「意外な展開だ」と唸らせたことだろう。
しかし個人的にはこのアイディアではなく、むしろ「超犯人」ガイの人物造形の方に興味がある。最終章で対峙したプリーストリー博士を前に己の計画を高らかに語ってみせる彼は、数々の綱渡りを見事に切り抜けて、一切の物的証拠をつかませぬまま計画を完遂した(あとで発見されたケースの中にヘクターの死体の痕跡が残っているとかそういう見落としがありそうなものだけれど、博士は一切言及しない)。ヘクター殺害の動機は「社会正義のため」、自分は一切の利益を得ぬまま数か月後には病で死ぬのだと嘯く彼に、博士はもはや反論しない。反論しないのか、できないのかは言及されないので分からない。博士はただ黙るだけである。個人的には、個人的な恨みを「社会のため」という言葉で糊塗しているようにしかみえないが、果たして作者はどう考えていたのやら。
そういえば、この「底なしの善人が社会悪を抹殺するために死にゆく自分の命を擲つ」という思想は、アントニイ・バークリー後期の傑作『試行錯誤』(1937)を思わせる。しかしあらゆる探偵小説が溢れ返る約10年間を経て、「法の裁きよりも真実の探求を」と謳う名探偵から反論を奪った麗しい題目が、滑稽なお笑い種へと転げ落ちていったというのはなかなか皮肉が利いている。
本作は、あらゆる意味で「20年代の傑作」というべき作品だと私は考える。
Martin Edwards, The Life of Crime が刊行されました
イギリスのミステリ作家/評論家のマーティン・エドワーズが年頭に自分のブログやフェイスブックにて「ミステリの歴史についての本を出します」と言っていたものが、 The Life of Crime という題でついに刊行されました。全世界的な流通の問題により(イギリス以外の)紙版は遅れて八月刊だそうですが、電子版は既にamazon kindle他で購入することができます。
この The Life of Crime は「1972年に刊行されたジュリアン・シモンズ『ブラッディ・マーダー』以来の、50年ぶりの総括的概説書」という惹句で売られていますが、エドワーズ曰く、シモンズの本とはかなり方向性を異にするものであるようです。
『ブラッディ・マーダー』は「探偵小説から犯罪小説へ」という副題からも分かる通り、「パズル的な『探偵小説』は人間の心理や社会を描く『犯罪小説』へと進化していく」という評論家シモンズの「思想」を論証する形で本文が構成されています。彼の意に沿わない、あるいは彼の好みから外れた作家は、論点から外され、また時に偏見にまみれた(ただし異様に切れ味のいい)罵言を投げつけられられました。その例が、文脈から排除されたことが明らかなドロシー・L・セイヤーズや、"Humdrum"(退屈派)と雑に括られたクロフツやジョン・ロードのような作家たちです。それでもなお、シモンズの評論は「ミステリ/探偵小説/犯罪小説」というあまりに膨大で、あまりに多岐に渡る小説群を総括的に論じた、という点から現代でも高く評価されています。
エドワーズは、本書ではシモンズと『ブラッディ・マーダー』の業績を評価しつつも、それとは異なる方向性を目指したと序文に記し、以下の三点を方針として示しました。すなわち、
①作品ではなく作家本位で書いたミステリ史であること(これは暴露本的な意味ではなく、作家を理解することによって彼らの作品を、そしてその連なりが作り出す「歴史」を理解することができると考えてのこと)
②シモンズとは真逆に、自分の好みの偏りや偏見を作品に反映させない、できるかぎりニュートラルな書き方を心掛けたこと。
③「ミステリ」という巨大なジャンルの全体像(黄金時代から現代へという時間軸を含めた)を捉えるのを重視したこと(その関係で、取り上げることのできなかった作家や作品が数多く存在するが、それらについては参考資料に示した作家の評伝や作品論を見てほしい)
本書は、ジャンルに属する膨大な作品群を、「矢印」のような「直線的な『進歩』の流れ」の中で評価するのではなく、ジャンルを大樹のように枝や根が多岐に分かれたものとしてイメージし、その全体像を評価するという姿勢を取っています。これは、作者が前著 The Story of Classic Crime in 100 Books (2017) で示したイメージと軌を同じくしています。The Story ~ でエドワーズは1950年頃までの古典ミステリのうち、そのすべてが必ずしも傑作とは言えないが、その時代の全体像を考える上では重要な100冊を取り上げて紹介しました。本書はその内容を拡大発展させたものと言えます。私も本文に取り組むのはこれからですが、読むのが今から楽しみです。
---
(参考)
以前、Re-ClaM誌に訳載した The Story of Classic Crime in 100 Books 序文の一部です。エドワーズの考え方を知る上での参考としていただければ。
---
[レビュー]ノエル・ヴァンドリー『逃げ出した死体』(同人出版、2013)
今月末に行われる第三十四回文学フリマ東京にて、「エニグマティカ」(テ-33)の中川潤氏(最近のお仕事は、白水uブックスから出たモーリス・ルヴェルの短編集『地獄の門』)がノエル・ヴァンドリー『獣の遠吠えの謎』(La Bête hurlante, 1934)を刊行されると聞いたので、日本で唯一紹介されているヴァンドリー作品を読んでみた。
この『逃げ出した死体』(La Fuite des morts, 1933)はROM叢書の第七巻として2013年に刊行された作品で、二段組みとは言え140ページほどで完結する短い長編である。アルー予審判事シリーズの第三作だが彼が登場するのは作品の後半で、そこまではマルティニェ警視とローラン予審判事が事件の捜査にあたる。あらすじは以下の通り。
---
カドゥアンというセールスマンが、「グレシーという男を殺した」と夜の街を巡回中の警察官に自白して出る。連絡を受けたマルティニェは事件現場とされる場所を確認するが、そこには血痕が残されているだけで死体は見あたらなかった。ところが同じ日、サポローという実業家が「グレシーを殺したので自殺する」という書き置きを残して失踪したことが明らかになる。懸命の捜査にもかかわらず消えた死体は一向に見つからず、しかしグレシーの妻、その愛人、さらには街を牛耳る脅迫者と容疑者ばかり次々に増えていく事態を前に、マルティニェとローランの捜査は混乱させられる。
---
1930年代のフランスの本格ミステリというと、英米の「パズラー」以上に「パズル」的な雰囲気が強いように勝手に思っていたが、その印象を裏切らない作品だ。登場人物の心理を書きこむ気などテンからない(被害者も関係者も極めて類型的・没個性的)極端な作風だが、ミスディレクションを利かせながら作りあげた物語をシンプルな(しかし入念な)どんでん返し一発でひっくり返す、という意外性に賭けて成功している。
「無暗に仮説など立てず、虚心坦懐に事実に向かい合うべし」と度々語るマルティニェが我慢できずに想像力を暴走させ、逆に彼にあまり手柄を立てさせたくないローランとの間で打打発止の議論を行う中盤は面白いがやや冗漫な部分もある。しかし、そこで組み立てられた理論を終盤で登場したアルーが再度分析、そこにマルティニェが「事件とは関係がない」と排除した些細な手がかりを組み込んでまったく異なる絵柄へと導くラストの展開は鮮やかなものだった(犯人が何でもかんでも説明してくれる結末はどうかと思う)。
本作について訳者の小林晋氏は「初頭幾何の問題が補助線一本引いただけで解けたような印象を受けた」と解説で書かれているがその表現には納得。氏が愛するレオ・ブルースの諸作にも近しい部分があると思う。
小林氏による解説は、ヴァンドリーの経歴や再発見の流れ、またアルー予審判事シリーズの全作品を子細に紹介した大変充実したもの。シリーズ第六作にあたる『獣の遠吠えの謎』へのコメントには「人間消失に城の中での密室殺人と、読者の興味をかき立てる。この作品でもミスディレクションの巧さが特徴的である」とあり、文学フリマ東京で刊行される中川氏の翻訳をぜひとも入手して読まなければと感じた。小林氏によるとアルー予審判事シリーズの最終作 À travers les murailles (1937、Through the Walls という題の英訳版がkindleで入手可能) がシリーズの集大成的な傑作で、本国の評論家の評価も高いとのこと。こちらもいずれ翻訳刊行されることを期待したい。
---
【後記(5/19)】
twitterで中川氏から連絡があったが、『獣の遠吠えの謎』は文学フリマには間に合わない可能性があり、初出は通販になるかもしれないとのこと。詳細の情報はご本人のtwitter(@Nakagawa_Jun)から告知されますので、ゲットしたい人はチェックを欠かさないようにして下さい。